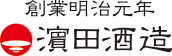こんにちは!新年度を迎え、気持ちも新たにがんばります!かじらーです。
桜が見頃を迎え、春本番となりました。4月に入り、新年度によって慌ただしい日々を過ごしている方も多いのではないでしょうか?
この時期は、心身の疲れが溜まりやすく、寝つきが悪くなりがちです。そんな夜、「寝酒」で眠りにつこうとする方もいらっしゃるかもしれません。ですが寝酒は、ときに逆効果になることも…。
今回は、お酒と睡眠の関係について、濵田酒造の産業医・萩原先生にお話を伺い、質の高い睡眠を得るためのヒントを教えていただきます!
「寝酒」はアリ?ナシ? 産業医の先生が教える睡眠に与えるアルコールの影響とは
――お酒を飲むと眠くなるのは、どうしてでしょうか?
萩原先生 アルコールを摂取すると、副交感神経が優位になり、気分がリラックスすることで眠気を感じやすくなります。
――では、「寝酒」というものがあるように、お酒は睡眠にとってプラスに働くのでしょうか。
萩原先生 アルコールを摂取することで副交感神経が優位となり眠れる、というのは適正なアルコール量を摂取した場合です。摂取量が多くなると、睡眠の質を悪化させ、かえって睡眠が足りなくなります。
アルコールは、一時的には寝つきを促進し睡眠前半では深い睡眠につながりますが、その効果は持続せず、睡眠後半の眠りの質は著しく悪化するそう。そして飲酒量が増加するにつれて中途覚醒回数が増え、結果的に睡眠不足の原因となることが報告されています。また、「寝酒」を繰り返すことで、アルコールを飲まないと眠れない状態になり、飲酒量の増加や不眠の悪循環に陥る可能性もあります。これらのことから厚生労働省でも、寝つきを改善するための飲酒「寝酒」は推奨していないのが実情です1。
――それでも、遅くまでの飲み会など避けられない状況も。そういったときに気を付けるべきこととは?
萩原先生 飲みすぎないことが一番です。飲みすぎにより、睡眠が足りなくなり、またアルコールが残った状態だと仕事にも影響がでることも。自分の適正な飲酒量を知り、その範囲内で楽しむことを心がけましょう。また空腹での飲酒は、アルコールの吸収が早いです。飲み会などでは、食事やおつまみを食べながら飲むようにしましょう。
自分にとっての「適正飲酒」を知り、質の高い眠りを目指そう!.png)
アルコールは体内に入ると、「アセトアルデヒド」という二日酔いの原因となる物質に分解されます。この物質は交換神経を刺激し、睡眠を阻害する物質を増加させるため、飲酒量とともにアルコールが分解される時間も重視する必要があります。アルコールの分解時間には個人差がありますが、一般的には純アルコール10gの排出に約2.5時間必要とされています。そのため適度な飲酒量の目安とされる20g(ロックでグラス1/2杯(100ml))を摂取すると、分解・排出されるまで約5時間かかることになります。
これらを目安に、飲酒量・分解時間・就寝時刻を調整することが、質の高い睡眠のためには重要です。
春の晩酌に、お湯割りで癒されるやさしいひとときを
お酒の中でも、本格焼酎はほかのお酒にはないメリットがたくさんあります!
単式蒸留焼酎によって生まれる豊かな香りや風味は本格焼酎ならではの魅力であり、特に芋焼酎の香りには、リラックス効果があるとされる「リナロール」という成分が含まれています。
この春には「お湯割り」がおすすめ。香りがふわっと引き立ち、ゆったりした晩酌の時間にぴったりです。温かいお湯割りは一気に飲むこともなく、ゆっくり味わうことで身体もじんわり温まります。
忙しい毎日や季節の変わり目で疲れを感じやすいこの時期こそ、お湯割りの「海童」で、ほっとひと息つく癒しの時間を過ごしませんか?
自分自身の「適量」を守りながら、素敵な“海童ライフ”を楽しみましょう!
それでは、次回の記事でお会いしましょう。
参考文献
厚生労働省 健康づくりのための睡眠ガイド2023
厚生労働省 健康に配慮した飲酒に関するガイドラインについて
厚生労働省が推進する国民健康づくり運動「健康日本21」